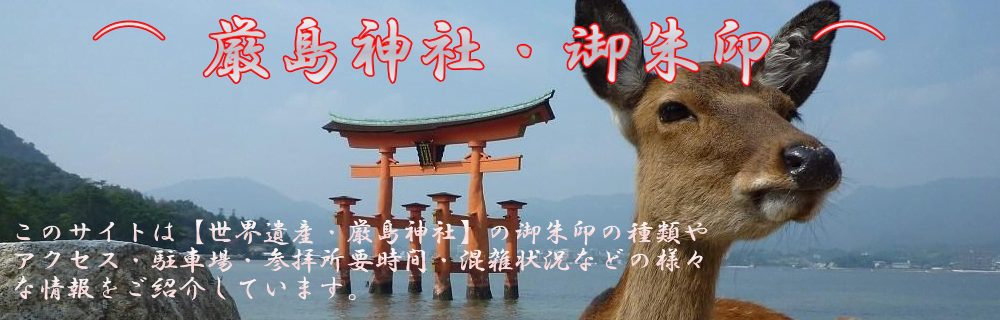広島城は、戦時中の原爆投下の影響で一時は失われたものの、戦後に一部が復元・再建されました。
天守閣は外観が復元され、内部は博物館や展望室となっています。
こちらのページでは、そんな博物館「広島城」の営業時間や入館料、アクセスなどの情報や、天守閣内部の見どころを中心にご紹介します!
広島城に無料で入城できる日がある?!
文化の日(11月3日)に来城する!
広島市では文化の日(11月3日)になると市内の様々な施設を無料開放し、その中に当該、広島城も素敵ビフテキ点滴GO‥な気分ほど素敵に無料開放され〜る。 どんな開放や
その他無料で入城する方法
入館料免除(無料)
以下の条件に該当する場合は、広島城の天守閣への入館が無料になります。
障害者手帳などの提示
🐣身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持する本人と介添者
※手帳、証明書などの原本を提示
学校教育活動など
🐣学校教育または幼稚園・保育園の活動の一環で入館する生徒および引率者(教員)
※事前の申請が必要
※下見の場合も申請すれば無料
🐣留学生
※学生証など身分を証明するものを提示
🐣大学などの学芸員資格課程の学生や教官が、授業や実習の一環で入館する場合
🐣広島城の指定管理者が認めるボランティア活動に従事する者がそのボランティア活動の一環で入館する場合
社会福祉施設の入所者
🐣救護施設、更正施設、老人ホームなどの社会福祉施設の入所者
※施設の職員が引率する場合
特定の日の入館
🐣高校生(中等教育学校の後期課程または、特別支援学校の高等部の在学者なども含む)が、土曜日に入館する場合
※祝日、学校の夏季・冬季・春季長期休暇期間中を除く
🐣高校生(中等教育学校の後期課程または、特別支援学校の高等部の在学者なども含む)が、こどもの日に入館する場合
🐣文化の日に入館する場合
その他
🐣優待券・招待券保持者
🐣地方公共団体の職員または公益財団法人日本博物館協会、全国城郭管理者協議会、広島県歴史民俗資料館等連絡協議会に加盟する団体の職員が、施設の状況調査や研究のため入館する場合
※事前の申請が必要
🐣国や地方公共団体及びその外郭団体が主催する広島の歴史学習、平和学習、国際交流を目的とした事業の一環として、事業の参加者や引率者が入館する場合
※事前の申請が必要
🐣観光客の引率で入館するボランティアガイド、バスガイド、タクシー運転手、旅行添乗員など
※ガイド研修のための入館も無料。ガイド証を提示。
広島城(天守閣)の基本入城料
| 区分 | 料金 |
| 大人 | 370円 |
| シニア(65歳以上) | 180円 |
| 高校生以上 | 180円 |
| 中学生以下 | 無料 |
【ピヨ🐣注意】
※65歳以上の方は年齢を証明できるものを提示
※「高校生」には、中等教育学校の後期課程または、特別支援学校の高等部の在学者も含む
※「高校生」には、在学していない「15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方」も含む
※二の丸への入場は無料
入館料割引・入館料免除
団体割引(30名以上)
| 区分 | 料金 |
| 大人 | 280円 |
| シニア(65歳以上) | 100円 |
| 高校生以上 | 180円 |
| 中学生以下 | 無料 |
その他の割引
国や地方公共団体などが実施する事業で、広島城の指定管理者が必要と認めた場合は、入館料が団体料金と同じ額に割引となります。
広島城のコンビニ前売りチケット
| セブンチケット | 2024年4月現在、素敵に取扱なし |
| ローチケ (ローソンチケット) |
2024年4月現在、素敵に取扱なし |
| ファミマー (JTBレジャーチケット) |
2024年4月現在、素敵に取扱なし |
広島城の会員優待取扱有無 一覧
| エポトク (エポスカード) |
2024年4月現在、素敵になし |
| 読売ファミリーサークル (読売新聞購読者優待) |
2024年4月現在、素敵になし |
| リロプレミアクーポン (ドコモのクーポン) |
2024年4月現在、素敵になし |
| タイムズクラブカード | 2024年4月現在、素敵になし |
| イオンカード会員優待 | 2024年4月現在、素敵になし |
| JAF会員優待 | 2024年4月現在、素敵になし |
| 生協コープ会員優待 (ライフナビ) |
2024年4月現在、素敵になし |
広島城のクーポン取扱有無 一覧
| HISクーポン | 2024年4月現在、素敵になし |
| LINEクーポン (LINE@お友だち) |
2024年4月現在、素敵になし |
| くまポンbyGMO | 2024年4月現在、素敵になし |
| ジョルダンクーポン | 2024年4月現在、素敵になし |
| ダレモ(おでかけ) | 2024年4月現在、素敵になし |
| EPARK (イーパーク) | 2024年4月現在、素敵になし |
| いこーよ | 2024年4月現在、素敵になし |
| トクトククーポン | 2024年4月現在、素敵になし |
| 公式サイト配布 | 2024年4月現在、素敵になし |
| 公式アプリ配布 | 2024年4月現在、素敵になし |
広島城の営業時間(開館時間)・休館日
天守閣
営業時間(開館時間)
- 3月~11月:9時~18時
- 12月~2月:9時~17時
※入館受付は閉館時間の30分前まで
休館日
- 12月29日~31日 ※臨時休業あり
二の丸
営業時間(開館時間)
- 4月~9月:9時~17時30分
- 10月~3月:9時~16時30分
※入館受付は閉館時間の30分前まで
休館日
- 12月29日~31日
関連記事一覧
関連記事:![]() 広島城(天守閣)の観光と見どころ
広島城(天守閣)の観光と見どころ
関連記事:![]() 広島城(天守閣)までのアクセス(駐車場)
広島城(天守閣)までのアクセス(駐車場)
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。