宮島・厳島神社「客神社」【国宝】
創建年
- 不明
- 推定:1176年(安元2年)※平安時代
再建年
- 1241年(仁治2年)※鎌倉時代
- 1430年(永享2年)※室町時代
建築様式(造り)
- 両流造
- 一重
屋根の造り
- 桧皮葺
大きさ
- 横幅:(桁行五間:約10m)
- 奥行:(梁間四間:約8m)
重要文化財指定年月日
- 1899年(明治32年)4月5日
国宝指定年月日
- 1952年(昭和27年)3月29日
主祭神
- 天忍穂耳命
- 活津彦根命
- 天穂日命
- 天津彦根命
- 熊野櫞樟日命
社格
- 厳島神社・摂社
宮島・厳島神社「客神社」の読み方
「客神社」は「きゃくじんじゃ」ではなく「まろうどじんじゃ」と読みます。
「客神社」の別名
清盛公が現在の社殿群を創建した頃は、「客宮(まろうどのみや)」もしくは「客人宮(まろうどのみや)」と呼ばれていたようです。
「客人」の名前の由来
とこで・・「まろうど」とは?
「まろうど」とは「客人」と書いて、客人をもてなすことを「まろうど」と呼称します。つまり、本殿で祀られている厳島神の客人をもてなす神様です。
厳島神社の客神社は、境内の入口に位置することから、この名前が付されたのであろうと推測されます。
宮島・厳島神社「客神社」の御祭神
「客神社」の御祭神は5柱の男性の神様をお祀りしています。
- 天忍穂耳命
- 活津彦根命
- 天穂日命
- 天津彦根命
- 熊野櫞樟日命
これら5柱の神様は、兄弟神であり「須佐之男命からお産まれになった御子神」です。厳島神社の主祭神である「宗像三女神」とは、同じタイミング(天照大御神と須佐之男命との契約)で産まれていることから兄弟神としても見られています。
厳島神社の主祭神である「宗像三女神」は、天照大御神が弟神の須佐之男命が持っていた「十拳剣(とつかのつるぎ)」を用いてお産みになられています。
一方、上記の「5柱神」は、須佐之男命が天照大御神から受け取った「勾玉」を用いてお産みになられています。
一般的には、この時に産まれた神々を「五男三女神」や「八王子」とも呼称しています。
ただし、上記の「天照大御神と須佐之男命の契約」の記述は「日本書紀」「古事記」双方に記述がありますが、双方で若干、内容が異なることから「諸説ある」と言う解釈になります。
天忍穂耳命
「天忍穂耳尊」 は「あまのおしほみみのみこと」と読みます。
この神様は一般的には「稲穂の神」「農業神」と位置づけられています。
活津彦根命
「活津彦根命」は「いきつひこねのみこと」と読みます。
この神様は「国家繁栄の神」「国造りの神」と云われています。
記紀においても記述がなく、子神がいないことから謎が多い神様です。
しかし、古くは織田信長によって国家鎮守を祈願し滋賀県東の「安土(あづち)の地」に奉じられ、後世では徳川四天王の井伊直政が彦根藩に封ぜられたことによって「井伊家の守護神」として祀られてきて歴史があります。
ちなみに「彦根」はこの神様の名前に因んだ地名と云われ、古来、変わらずに彦根の地元では土地神として崇敬を集めています。
天穂日命
「天穂日命」は「あめのほひのみこと」と読みます。
この神様は一般的に「農業の神」と位置づけられています。
天津彦根命
「天津彦根命」は「あまつひこねのみこと」と読みます。
この神様は一般的に「日の神」「雨の神」「風の神」「火難除けの神」と位置づけられています。
熊野櫞樟日命
熊野櫞樟日命は「くまのくすびのみこと」と読みます。この神様は「五穀豊穣の神」と云わます。謎の多い神様でもあり、記紀においても記述がほとんど残っていません。
宮島・厳島神社「客神社」の建築様式(造り)
厳島神社の客神社も本殿と同じく「両流造」で造営されています。しかし実のところ、この客神社の殿舎の造りは、社殿そのものを本殿をひとまわり小さくして本殿を縮小しただけの殿舎になっています。つまり本殿と社殿の造りは基本、同じとされています。
よって社殿全体の配置も手前から「祓殿⇒拝殿⇒幣殿⇒本殿」と配し、本殿の構造とまったく同じです。
これはつまり、客神社が単に客人を出迎えるための入口付近に建てられた神社ではなく、本殿に次ぐ格式を持った神社であると位置付けることができます。
本殿に次ぐ格式を持つ客神社
この客神社が本殿に次ぐ格式を持つ神社であるとされる理由は、客神社の社殿内の建築様式を見ることでつぶさに理解ができるというものです。
例えば、もっともハッキリとする特徴としては客神社内に据えられた「折上式小組格天井」があります。
折上式小組格天井は天皇の宮殿に用いられるような格式高い建築様式です。「折上げ式」とは、天井をそのまま平行に張らずに一段さらに天上部へ上げた天井のことです。一段上がっていように見えますので奥行きが備わって高級感が生まれます。
小組み格天井とは、細かな正方形のマス枠を張りめぐらせた天井のことです。一般の天井と比較すれば比べものにならないぐらいの手間と費用がかかります。
このように一見すると本殿と造りがまったく同じように見えますが、所々で本殿との造りに違いが見受けられます。
厳島神社の本殿と客神社との建築様式(造り)の違い
横幅が違う
上述のように客神社の造りは、本殿をそのまま縮小したような造りのため、一見すると本殿と全く同じ造りに見えますが、よく見ると造りに相違があることに気づきます。
もっとも大きな違いとしては、客神社の本殿は規模が異様に小さく、厳島神社・本殿と比べて横幅が8mほども小さい造りになっています。
回廊の位置は客神社が「祓殿」と「拝殿」の間を通る造りになっているのに対し、本殿は「祓殿」を回り込むような形で西回廊へ接続されています。
また、客神社では本殿に比べて拝殿が小さく、拝殿としてのスペースを確保するために、柱の数を減らして柱間を広く保つ造りになっています。
屋根の形状が違う
屋根は本殿の入母屋造に対して、客神社では庇(ひさし)を付けることによって完全な入母屋造としていません。
また社殿の後方部の「化粧屋根裏天井」も、本殿では二間それぞれに備え付けているのに対して、客神社では二間分を「一本通しの化粧屋根裏天井」として設置しています。
殿舎正面の扉が違う
「正面・開口部の仕切り」は、本殿では「網目状(蔀/しとみ)」になっており、客神社では「網目がない仕切り扉(舞良戸/まいらど)」になっています。
客神社の歴史・由来
客神社の創建は不明となっており、現在見ることのできる客神社の姿は1430年(室町時代)に行われた大改修の時の姿を濃く残していると云われています。
厳島神社は過去に2回ほど大火事に見舞われており、その都度、再建されてきた歴史があります。
尚、根本的な社殿群の姿は1168年の平清盛による大造営の時のものですが、本殿以外の社殿群の現在の姿は1241年(仁治2年)に再建された時のものが、そのほとんどであると云われています。
【補足】厳島神社の境内摂社・客神社の構成
宮島・厳島神社・境内摂社「客神社・拝殿」
建築様式(造り)
- 切妻造
- 両端屋根庇付き
- 一重
屋根の造り
- 桧皮葺
大きさ
- 桁行九間(横幅:18m)
- 梁間三間(縦幅:6m)
宮島・厳島神社・境内摂社「客神社・幣殿」
建築様式(造り)
- 両下造
屋根の造り
- 桧皮葺
大きさ
- 桁行一間(横幅:2m)
- 梁間一間(縦幅:2m)
宮島・厳島神社・境内摂社「客神社・祓殿」
建築様式(造り)
- 入母屋造
- 妻入
屋根の造り
- 桧皮葺
大きさ
- 桁行四間(横幅:8m)
- 梁間四間(縦幅:8m)
その他にも、実は厳島神社における客神社は入口のみにあるのではなく、境内の舞台の両端にも造営されており、これらを「右門客神社(みぎかどまろうどじんじゃ)」「左門客神社(ひだりかどまろうどじんじゃ)」と呼称します。いずれの社も御祭神がそれぞれに異なっています。
これらの両社の存在は、上述の入口に位置する客神社・本殿を「守護するための社」であると伝えられています。
厳島神社を参拝する時はまず、この客神社から!
厳島神社を参拝する際は、まず、この客神社から参拝するのが正式とされています。
本土の宮島口からフェリーへ乗船して、宮島の桟橋に到着したら、そのまま海岸沿いを歩いて厳島神社を目指します。
そして厳島神社の入口に入ると真っ先に参拝客を出迎えてくれるのがこの客神社です。
入口の手水舎でおチェチェ(訳:手)と口を清めたあとは、まずはこの客神社へ立ち寄って、自分の名前とドコから参拝に来たのかを小さくボソボソとつぶやきながら祈願をしてみてください。 ただしあまりにもボソボソが長いと勘違いされて逮捕される恐れがありますのでご注文下さ、・・あイヤイヤご注意下さい。ウフ
客神社の場所(地図)
客神社は厳島神社の境内入口となる「東廻廊」から入って最初に参拝者を出迎えてくれる殿舎になります。
鈴はなく賽銭箱へ賽銭を投入して祈願する形式になります。
関連記事一覧
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。
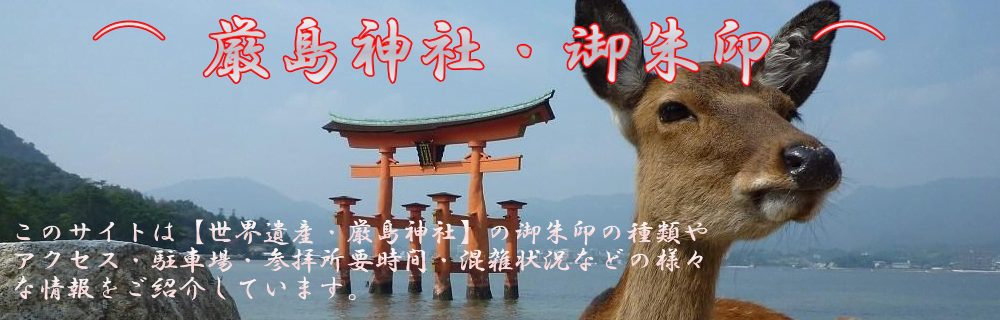





-.jpg)